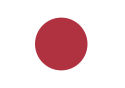日本占領時期のイギリス領ボルネオ
この項目「日本占領時期のイギリス領ボルネオ」は途中まで翻訳されたものです。(原文:en:Japanese occupation of British Borneo) 翻訳作業に協力して下さる方を求めています。ノートページや履歴、翻訳のガイドラインも参照してください。要約欄への翻訳情報の記入をお忘れなく。(2019年12月) |
- 北ボルネオ
- North Borneo (英語)
-
← 
←
←
←
1941年 - 1945年  →
→ 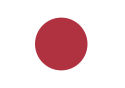

(大日本帝国の旗) (菊花紋章) - 国の標語: 八紘一宇
- 国歌: 君が代

1943年のボルネオの日本占領地の地図-
公用語 日本語 言語 マレー語
中国語
ボルネオ語首都 クチン[1][2] 通貨 大日本帝国政庁発行の軍票
(俗称:バナナ・マネー)現在  ブルネイ
ブルネイ マレーシア
マレーシア
日本占領時期のイギリス領ボルネオ(にほんせんりょうじきのイギリスりょうボルネオ)では、ボルネオ島のイギリス植民地が太平洋戦争中に日本に占領統治されていた時期について記述する。
戦争前、ボルネオ島は5つの領域に分割されていた。そのうち4つは北部にあり、イギリスの支配下にあった。サラワク、ブルネイ、島嶼のラブアンと、英領北ボルネオがそれに該当する。島の残りの大部分はオランダ領東インドの管轄下にあった。
1941年12月16日、フランス領インドシナのカムラン湾から出撃した日本軍がサラワクのミリに上陸した。日本が島全体を征服するのには1か月も要しなかった。日本はその後、北部を「北ボルネオ」、ラブアンを「前田島」、隣接するオランダ領を「南ボルネオ」とした[5][6][7]。近代史上初めて、ボルネオ島全体が単一の法体系によって支配された[8]。
イギリス領ボルネオは3年以上にわたり日本に占領されていた。日本人は、日本語と日本の習慣を学ぶことを地元住民に要求して、皇民化を積極的に促進した。日本人は北ボルネオを5つの地方行政区分(州)に分割し、飛行場を建設した。捕虜収容所が数カ所、日本人によって運営された。連合軍の兵士とほとんどの植民地の役人は、日本占領に反対した地下運動のメンバーと一緒に拘留された。一方、地元のマレー人指導者は日本の監視下に置かれ、多くの外国人労働者がこの地域に移送された。
1945年の終わり頃までの間、オーストラリア軍コマンド部隊がアメリカ海軍の潜水艦によって島に配備され、連合軍の解放を任務とした主要部隊を送り込むのに備えてZ特殊部隊が情報活動をおこなって先住民に日本と戦うゲリラ戦の訓練を施した。1945年6月10日からオーストラリア・アメリカ連合軍が北ボルネオおよびラブアンに上陸した後、ボルネオ島は解放された。1945年9月12日にボルネオイギリス軍政部が日本から正式に統治を引き継いだ。
背景[編集]
日本がボルネオの支配権を掌握するという意向は、大東亜共栄圏の構想と関連していた。これは1936年から1940年に外務大臣を務めた軍国主義者の有田八郎によって企図された[9]。日本の指導者は、西欧からの干渉を受けずに東京から指導されるアジアを構想し、大日本帝国をモンロー主義のアジア版になぞらえた[10]。ボルネオ島は、ジャワ・スマトラ・マラヤ・セレベスの間の主な航路上に位置することから、戦略上重要とみなされた。これらの航路の管理は、この地域を守る上で不可欠だった[11][12]。

日英同盟により、1900年代以降日本人の移民は歓迎されていた。三菱や日産自動車などの企業はこの地域で貿易をおこなっていた[7][11][13]。日本の移民は1915年からサラワク王国に居住し、行商で働く者や風俗街に勤める女性もいた[14]。特に1930年代以降は、日本軍によるスパイ活動が移民に見られるようになった[11][15]。極秘電報は、コタキナバルで定期的にドック入りする日本船舶がスパイ活動と関連していることを暴露した[16]。
1940年にアメリカとイギリスは、日本が中国侵攻と仏印進駐を継続していることを理由に、日本に対する原材料について通商停止をおこなった[17][18][19][20]。日本は太平洋地域での覇権を握る長期目標のために、慢性的に不足する天然資源、とりわけ原油を必要とした[14][21]。東南アジアはその大半が西欧の植民地で構成されており、やがて日本の主要な標的となった。西欧の植民地支配を終わらせるとともに資源の確保が期待された[22][23][24][25]。
侵攻[編集]
日本の侵攻作戦は、イギリス領は大日本帝国陸軍に、オランダ領は大日本帝国海軍に指令された[26]。陸軍は第35歩兵旅団がボルネオを担当した。旅団は川口清健少将が指揮し、以前には中国南部の広州に駐留していた部隊によって編成されていた[27]。1941年12月13日、日本の船団は、フランス領インドシナ(現・ベトナム)のカムラン湾を出航。船団の護衛は、軽巡洋艦「由良」および第三水雷戦隊第12駆逐隊(「叢雲」「東雲」「白雲」「薄雲)、第七号駆潜艇、特設水上機母艦「神川丸」だった。10隻の兵員輸送船が侵攻部隊の先発隊を運んだ。栗田健男少将が指揮する重巡洋艦「鈴谷」「熊野」および駆逐艦「吹雪」「狭霧」が支援部隊だった[28]。日本軍は、ミリとセリアの占領後にクチンおよび近くの飛行場に進撃することを企図した[28]。輸送船団は発見されることなく進み、12月16日の夜明けに2つの上陸部隊はイギリス軍の抵抗をほとんど受けずに、ミリとセリアを制圧した[28]。
経済[編集]
占領後、1941年12月26日に官庁が再開された[29]。日本企業が設立され、必需品の独占が認められた。1942年初頭、横浜正金銀行の最初の支店がクチンの旧チャータード銀行の建物に開設された。また、日本の拓務省は、ボルネオ島北部全体の投資を監督する事務所を開設した。東京海上火災と三菱海上火災の2つの日本の保険会社(いずれも東京海上日動火災保険の前身)が営業を開始した[29]。
すべての自動車は、限られた補償で日本運輸株式会社によって没収された。日本人は労働者を雇い、追加の食料と支払いのために飛行場を建設したが、被拘禁者は働くことを余儀なくされた[29][30]。他の東南アジアとともに、日本は原材料の供給源としてボルネオを利用した[31] [32]。盗みや密輸は死刑に処せられた。陸海軍は、日本の戦争遂行を目的として、石油産業の再建を試みた[33][34][注 1]。

解放[編集]
脚注[編集]
注釈[編集]
- ^ 平川均&清水宏 (2002)は、『からゆきさんと経済進出―世界経済のなかのシンガポール‐日本関係史』コモンズ、1998年の英訳。
出典[編集]
- ^ 日本サラワク協会 1998.
- ^ Kratoska 2013, p. 111.
- ^ The population was made up of:
Sarawak: 580,000;
Brunei: 39,000;
North Borneo: 331,000 - ^ Vinogradov 1980, p. 73.
- ^ Ooi 2010, p. 133.
- ^ Braithwaite 2016, p. 253.
- ^ a b Jude 2016.
- ^ Baldacchino 2013, p. 74.
- ^ 入江昭 2014, p. 76.
- ^ 川村のり子 2000, p. 134.
- ^ a b c Jackson 2006, p. 438.
- ^ Broch 1943.
- ^ Akashi & Yoshimura 2008, p. 23.
- ^ a b Ringgit 2015.
- ^ 商工省商務局 1930.
- ^ 白石さや & 白石隆 1993, p. 54.
- ^ Kennedy 1969, p. 344.
- ^ Rogers 1995, p. 157.
- ^ D. Rhodes 2001, p. 201.
- ^ Schmidt 2005, p. 140.
- ^ Black 2014, p. 150.
- ^ Mendl 2001, p. 190.
- ^ Lightner Jr. 2001, p. 30.
- ^ Steiner 2011, p. 483.
- ^ Dhont, Marles & Jukim 2016, p. 7.
- ^ Ooi 2013, p. 15.
- ^ Rottman 2013, p. 17.
- ^ a b c Klemen 2000.
- ^ a b c Ooi 1999, p. 125.
- ^ Braithwaite 1989, p. 157.
- ^ Hong 2011, p. 232.
- ^ Ooi 2010, p. 112.
- ^ de Matos & Caprio 2015, p. 43.
- ^ 平川均 & 清水洋 2002, p. 133.
参考文献[編集]
- 商工省商務局 編『神秘境英領北ボルネオ』文原堂、1930年。
- Broch, Nathan (1943年). “Japanese Dreams in Borneo”. The Sydney Morning Herald. Trove. 2017年10月1日閲覧。
- The Mercury (1) (1947年). “Four Japs General for Trial”. The Mercury (Hobart). Trove. 2017年10月16日閲覧。
- The Mercury (2) (1947年). “Death Sentence for Japanese General”. The Mercury (Hobart). Trove. 2017年10月16日閲覧。
- The Argus (1947年). “Jap General will die for ‘death march’”. The Argus (Melbourne). Trove. 2017年10月16日閲覧。
- The Sydney Morning Herald (1947年). “Japanese to be Hanged”. The Sydney Morning Herald. Trove. 2017年10月16日閲覧。
- Tregonning, K. G. (1960). North Borneo. H.M. Stationery Office
- Keogh, Eustace (1965). The South West Pacific 1941–45. Grayflower Productions. OCLC 7185705
- Dod, Karl C. (1966). Technical Services, Corps of Engineers, the War Against Japan. Government Printing Office. ISBN 978-0-16-001879-4
- Alliston, Cyril (1967). Threatened Paradise: North Borneo and Its Peoples. Roy Publishers
- Kennedy, Malcolm Duncan (1969). The Estrangement of Great Britain and Japan, 1917–35. Manchester University Press. ISBN 978-0-7190-0352-3
- Luping, Margaret; Chin, Wen; Dingley, E. Richard (1978). Kinabalu, Summit of Borneo. Sabah Society
- FitzGerald, Lawrence (1980). Lebanon to Labuan: a story of mapping by the Australian Survey Corps, World War II (1939 to 1945). J.G. Holmes Pty Ltd.
- Vinogradov, A.G. (1980). The population of the countries of the world from most ancient times to the present days: Demography. WP IPGEB. GGKEY:CPA09LBD5WN
- Watt, Donald Cameron (1985). The Tokyo War Crimes Trial: Index and Guide. Garland. ISBN 978-0-8240-4774-0
- Nelson, Hank (1985). P.O.W., prisoners of war: Australians under Nippon. ABC Enterprises. ISBN 978-0-642-52736-3
- Abbas, Ismail; Bali, K. (1985) (Malay). Peristiwa-peristiwa berdarah di Sabah. Institute of Language and Literature, Ministry of Education (Malaysia)
- Chay, Peter (1988). Sabah: the land below the wind. Foto Technik. ISBN 978-967-9981-12-4
- Braithwaite, John (1989). Crime, Shame and Reintegration. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-35668-8
- Wall, Don (1990). Abandoned?: Australians at Sandakan, 1945. D. Wall. ISBN 978-0-7316-9169-2
- Lee, Sheng-Yi (1990). The Monetary and Banking Development of Singapore and Malaysia. NUS Press. ISBN 978-9971-69-146-2
- Evans, Stephen R. (1990). Sabah (North Borneo): Under the Rising Sun Government. Tropical Press
- Reece, Bob (1993). Datu Bandar Abang Hj. Mustapha of Sarawak: some reflections of his life and times. Sarawak Literary Society
- 白石さや; 白石隆 (1993). The Japanese in Colonial Southeast Asia. SEAP Publications. ISBN 978-0-87727-402-5
- Rogers, Robert F. (1995). Destiny's Landfall: A History of Guam. University of Hawaii Press. ISBN 978-0-8248-1678-0
- 日本サラワク協会, ed (1998). 北ボルネオ・サラワクと日本人:マレーシア・サラワク州と日本人の交流史. せらび書房. ISBN 978-4-915961-01-4
- Coulthard-Clark, Chris (1998). The Encyclopaedia of Australia's Battles. Allen & Unwin. ISBN 1-86448-611-2
- Heimann, Judith M. (1998). The Most Offending Soul Alive: Tom Harrisson and His Remarkable Life. University of Hawaii Press. ISBN 978-0-8248-2199-9
- Ooi, Keat Gin (1999). Rising Sun over Borneo: The Japanese Occupation of Sarawak, 1941–1945. Palgrave Macmillan UK. ISBN 978-1-349-27300-3
- Fuller, Thomas (1999年). “Borneo Death March /Of 2,700 Prisoners, 6 Survived : An Old Soldier Remembers a Wartime Atrocity”. The New York Times. 2017年9月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年9月22日閲覧。
- Klemen, L. (2000年). “The Invasion of British Borneo in 1942”. Dutch East Indies Webs. 2017年9月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年9月19日閲覧。
- 川村のり子 (2000). Turbulence in the Pacific: Japanese-U.S. Relations During World War I. Greenwood Publishing Group. ISBN 978-0-275-96853-3
- Towle, Philip; Kosuge, Margaret; Kibata, Yoichi (2000). Japanese Prisoners of War. A&C Black. ISBN 978-1-85285-192-7
- D. Rhodes, Benjamin (2001). United States Foreign Policy in the Interwar Period, 1918-1941: The Golden Age of American Diplomatic and Military Complacency. Greenwood Publishing Group. ISBN 978-0-275-94825-2
- Tarling, Nicholas (2001). A Sudden Rampage: The Japanese Occupation of Southeast Asia, 1941-1945. C. Hurst & Co. Publishers. ISBN 978-1-85065-584-8
- Lightner Jr., Sam (2001). All Elevations Unknown: An Adventure in the Heart of Borneo. Crown/Archetype. ISBN 978-0-7679-0949-5
- Mendl, Wolf (2001). Japan and South East Asia: From the Meiji Restoration to 1945. Taylor & Francis. ISBN 978-0-415-18205-8
- Jack, Wong Sue (2001). Blood on Borneo. L Smith (WA) Pty, Limited. ISBN 978-0-646-41656-4
- Thurman, Malcolm Joseph; Sherman, Christine (2001). War Crimes: Japan's World War II Atrocities. Turner Publishing Company. ISBN 978-1-56311-728-2
- 平川均; 清水洋 (2002). Japan and Singapore in the World Economy: Japan's Economic Advance into Singapore 1870-1965. Routledge. ISBN 978-1-134-65173-3
- Welch, Jeanie M. (2002). The Tokyo Trial: A Bibliographic Guide to English-language Sources. ABC-CLIO. ISBN 978-0-313-31598-5
- Johnston, Mark (2002). That Magnificent 9th: An illustrated history of the 9th Australian Division 1940-46. Allen & Unwin. ISBN 1-86508-654-1
- Likeman, Robert (2003). Men of the Ninth: A History of the Ninth Australian Field Ambulance 1916-1994. Slouch Hat Publications. ISBN 978-0-9579752-2-4
- Danny, Wong Tze-Ken (2004). Historical Sabah: The Chinese. Natural History Publications (Borneo). ISBN 978-983-812-104-0
- Feuer, A. B. (2005). Australian Commandos: Their Secret War Against the Japanese in World War II. Stackpole Books. ISBN 978-0-8117-3294-9
- Schmidt, Donald E. (2005). The Folly of War: American Foreign Policy, 1898-2005. Algora Publishing. ISBN 978-0-87586-382-5
- Jackson, Ashley (2006). The British Empire and the Second World War. A&C Black. ISBN 978-1-85285-417-1
- Bullard, Steven (2006年). “Human face of war (Post-war Rabaul)”. Australian War Memorial. Australia-Japan Research Project. 2017年10月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年10月15日閲覧。
- Akashi, Yōji; Yoshimura, Mako (2008). New Perspectives on the Japanese Occupation in Malaya and Singapore, 1941–1945. NUS Press. ISBN 978-9971-69-299-5
- Heimann, Judith M. (2009). The Airmen and the Headhunters: A True Story of Lost Soldiers, Heroic Tribesmen and the Unlikeliest Rescue of World War II. Houghton Mifflin Harcourt. ISBN 0-547-41606-7
- Felton, Mark (2009). Japan's Gestapo: Murder, Mayhem and Torture in Wartime Asia. Pen & Sword Military. ISBN 978-1-84415-912-3
- Lebra, Joyce (2010). Japanese-trained Armies in Southeast Asia. Institute of Southeast Asian Studies. ISBN 978-981-4279-44-4
- Ooi, Keat Gin (2010). The Japanese Occupation of Borneo, 1941-45. Routledge. ISBN 978-1-136-96309-4
- Tourism Malaysia (2010年). “Labuan War Cemetery”. Tourism Malaysia. 2017年10月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年10月17日閲覧。
- Tan, Gabriel (2011年). “Under the Nippon flag”. The Borneo Post. 2017年8月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年8月4日閲覧。
- Hong, Bi Shi (2011年). “Japan’s Economic Control in Southeast Asia during the Pacific War: Its Character, Effects and Legacy”. School of International Studies, Yunnan University. Waseda University. 2021年11月6日閲覧。
- Steiner, Zara (2011). The Triumph of the Dark: European International History 1933–1939. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-921200-2
- Trefalt, Beatrice (2013). Japanese Army Stragglers and Memories of the War in Japan, 1950–75. Routledge. ISBN 978-1-134-38342-9
- Baldacchino, G. (2013). The Political Economy of Divided Islands: Unified Geographies, Multiple Polities. Springer. ISBN 978-1-137-02313-1
- Rottman, Gordon L. (2013). Japanese Army in World War II: The South Pacific and New Guinea, 1942–43. Bloomsbury Publishing. ISBN 978-1-4728-0466-2
- Saunders, Graham (2013). A History of Brunei. Routledge. ISBN 978-1-136-87394-2
- Ooi, Keat Gin (2013). Post-war Borneo, 1945-50: Nationalism, Empire and State-Building. Routledge. ISBN 1-134-05803-9
- Ham, Paul (2013). Sandakan. Transworld. ISBN 978-1-4481-2626-2
- Kratoska, Paul H. (2013). Southeast Asian Minorities in the Wartime Japanese Empire. Routledge. ISBN 978-1-136-12514-0
- Daily Express (2013年). “Granddaughter seeks apology for massacre”. Daily Express. 2017年10月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年10月18日閲覧。
- 入江昭 (2014). Japan and the Wider World: From the Mid-Nineteenth Century to the Present. Taylor & Francis. ISBN 978-1-317-89407-0
- Daily Express (2014年). “Looking back: North Borneo war scars”. Daily Express. 2017年10月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年10月18日閲覧。
- Black, Jeremy (2014). Introduction to Global Military History: 1775 to the Present Day. Routledge. ISBN 978-1-317-79640-4
- de Matos, Christine; Caprio, M. (2015). Japan as the Occupier and the Occupied. Palgrave Macmillan UK. ISBN 978-1-137-40811-2
- Ringgit, Danielle Sendou (2015年). “Sarawak and the Japanese occupation”. The Borneo Post Seeds. 2017年9月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年9月21日閲覧。
- Wiesman, Hans (2015). The Dakota Hunter: In Search of the Legendary DC-3 on the Last Frontiers. Casemate. ISBN 978-1-61200-259-0
- 角南聡一郎「アジアにおける日本人墓標の諸相 : その記録と研究史」『人文学報』第108号、京都大學人文科學研究所、2015年、3-20頁、doi:10.14989/204513、ISSN 0449-0274、NAID 120005704195。
- Tay, Frances (2016年). “Japanese War Crimes in British Malaya and British Borneo 1941–1945”. Japanese War Crimes Malaya Borneo. 2017年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年10月6日閲覧。
- Dhont, Frank; Marles, Janet E.; Jukim, Maslin (2016). “Memories of World War II: Oral History of Brunei Darussalam (Dec. 1941 – June 1942)” (PDF). Universiti Brunei Darussalam (Institute of Asian Studies). オリジナルの23 September 2017時点におけるアーカイブ。.
- Fitzpatrick, Georgina; McCormack, Timothy L.H.; Morris, Narrelle (2016). Australia's War Crimes Trials 1945–51. BRILL. ISBN 978-90-04-29205-5
- Jude, Marcel (2016年). “Japanese community in North Borneo long before World War II”. The Borneo Post. PressReader. 2017年10月1日閲覧。
- Braithwaite, Richard Wallace (2016). Fighting Monsters: An Intimate History of the Sandakan Tragedy. Australian Scholarly Publishing. ISBN 978-1-925333-76-3
- 村岡崇光 (2016). My Via Dolorosa: Along the Trails of the Japanese Imperialism in Asia. AuthorHouse UK. ISBN 978-1-5246-2871-0
- Woodward, C. Vann (2017). The Battle for Leyte Gulf: The Incredible Story of World War II's Largest Naval Battle. Skyhorse Publishing. ISBN 978-1-5107-2135-7
- Chandran, Esther (2017年). “Discovering Labuan and loving it”. The Star. 2017年8月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年8月17日閲覧。
- Welman, Frans (2017). Borneo Trilogy Volume 1: Sabah. Booksmango. ISBN 978-616-245-078-5
- Labuan Corporation (1) (2017年). “Peace Park (Taman Damai)”. Labuan Corporation. 2017年8月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年8月14日閲覧。
- Labuan Corporation (2) (2017年). “Surrender Point”. Labuan Corporation. 2017年10月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年10月14日閲覧。
- 田中利幸 (2017). Hidden Horrors: Japanese War Crimes in World War II. Rowman & Littlefield Publishers. ISBN 978-1-5381-0270-1


 French
French Deutsch
Deutsch